あなたは、端午の節句に、ちまきを手作りしてお祝いしたいけれど、
- どんな材料をそろえたらいいかわからない。
- 材料をどこで買ったらよいのかわからない。
- 作り方がわからない
とお悩みではありませんか?
今日は、実際にちまきを手作りした私が、おすすめの材料や作り方をご紹介します。
私は、今回初めてちまき作りに挑戦しましたが、とても楽しく、おいしく作ることができたので、
あなたもぜひ参考にしてみてくださいね。
ちまきの作り方 おすすめの材料と口コミをご紹介
ちまきを手作りする材料を探すにあたって、あんこがおいしいと評判のあんこの内藤さんにお電話をして、「ちまきの手作りセットはないのでしょうか?」と伺いました。
でも残念ながら、粽(ちまき)の手作りセットはない、とのことでした。
「当店では、もち粉と笹はございますが、粽の手作りセットとしてはないのです。
なにかレシピをご覧になって、おつくりいただければと思います。申し訳ございません。」とのことでした。
そこで、自分で、「笹 ちまき」「ちまき 手作り」などと検索をしたり、お菓子作りの材料といえば富澤商店が有名だったな~と思い出して調べたりして、以下の材料をそろえました。
- 笹…あんこの内藤
- もち粉・・・あんこの内藤
- 井草・・・富澤商店
それでは、それぞれの材料について商品の特徴や口コミをご紹介していきます(^^♪
あんこの内藤 笹(軸付き)商品内容
| 内容量 | 50枚 |
| サイズ | 長さ:葉 約30cm 軸 約18cm 幅 :約6cm ※およその大きさになります。天然のものなので大きさに多少のばらつきがあります。 |
| 産地 | 青森県 |
| 保存方法 | 常温20度以下で保存すること |
| 使い方 | 沸騰したお湯で戻してから使用すること |
青森県から取り寄せた軸付きの笹の葉を乾燥させて商品です。
国産の笹の葉は、嬉しいですよね。
残念ながら口コミがありませんでした。
調べているときに国産でなくて残念、との口コミがあったので、
国産の笹を扱っているお店をくまなく探しました。
さすがは人気の和菓子店内藤さんですね。
安心して使えますね。
内藤さんには、ちまきづくりに最適と業務用の300枚入り商品がありますが、
「きれいな笹でちまきづくりがうまくできた」という口コミがありました。
あんこの内藤 もち粉 商品内容&口コミ
| もち粉 | |
| 内容量 | 150g |
| 賞味期限 | 6か月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温20度以下で保存のこと |
| 原材料 | もち米(国産) |
もち米を精白し手洗いして、粉にし、乾燥させたものだそうです。
良い口コミ
・イチゴ大福に重宝している
・レンジで和菓子がおいしくできる
・餅菓子がおいしくできる
・ケーキがおいしく作れた
・娘と楽しく和菓子が作れた
・近くに売っていないので助かる
・安くてうれしい
富沢商店 井草
「いぐさ」なのか、「すげ」なのか、とふと思われる方もいるかもしれません。
井草は、しなやかで弾力があるので、初心者にも扱いやすいといわれています。
| 商品名 | 井草(いぐさ) |
| 内容量 | 50g |
| 保存方法 | 冷暗所で保存 |
| 保存期限 | 未開封時の場合:特になし 開封後は早めに使用すること |
| 使い方 | 熱湯でさっと湯がくか、半日ほど水に浸してから使用のこと |
| 注意事項 | 食べられません |
特にネット上の口コミはなかったのですが、実際に使ってみて、本当に使いやすかったですよ~(^^♪
使い方は次の章で詳しくご紹介しますね!
ちまきの作り方を写真付きでご紹介
それでは、取り寄せた材料をご覧下さい。
まずは、あんこの内藤のもち粉

そして、あんこの内藤の笹。
新聞紙にきれいに包まれて届きました。

最後に、3つ目の材料富沢商店の井草。

ちまきづくりの3種の神器を手に、いよいよ手作り開始です!
いざ出陣~!😊🤭
ちまきの作り方
家にある料理の本や、ネット上のいろいろなレシピや動画、良平堂の柏餅とちまきセットを参考にして作りました。
<食材>
・もち粉 150g
・熱湯 約100㏄
・砂糖 約25g
お砂糖は、もち粉を少し戴くと、あなたのお好みの分量がわかると思います。
私が参考にしたレシピの中には、お砂糖を使用しないで作ってらした方もいました。
そこで、私は、粉を少し戴いてみました。
ちょっとお砂糖をいれたほうががいいな、と感じたのでお砂糖は、約25g入れました。
作り方
1.もち粉と、砂糖を混ぜる
2.熱湯を入れ混ぜる

3.ラップをしてレンジで2,3分調理する
4.混ぜる
5.ラップをしてレンジで2分調理する
6.よくこねる
7.棒状(紡錘型)に形成する

それでは、いよいよ笹に包んでいきます。
材料:ちまき1個分
・笹の葉 2枚
・イグサ 1本
1.笹の葉と、井草は、半日水につけるか、お湯で5分くらい湯がく
2.笹の葉の表にちまきを乗せる
3.笹の葉でちまきを包む
水でよく濡らすと作業がしやすいですよ。


4.葉先は織り込まないで、
葉の両側を合わせるように包む
4.包んだちまきの背面を上にして、
もう1枚の笹(裏側)の上に乗せて、包む

5.葉の両側を内側に合わせるように包み込む
ワイヤーの入ったラッピンググッズを使うと作業がしやすいですよ。

6.井草(約2m)の茎を
粽を包んだ笹と、
外側の笹との間にさしこむ

7.葉先2枚を井草で2回まく

8.3回目に葉先2枚を一緒に
笹の合わさり部分に差し込む

9.くるくるとらせん状にイグサを巻き付ける
長くても切らないでくださいね。
私は非常に工作や手芸が苦手で不器用です😅
おゆるしを。
左側が初めて作った1回目。
右側が、2回目です。

10.3つ作りました😅
恥ずかし~🤣

11.3つをひとまとめにする
笹の茎と、井草の残りの部分をきちんと分け、見やすくするとよいです😊

12.井草の葉先を10センチくらい残すところまで巻く
13.ちまきを裏返して、笹の茎を巻き付ける
ワイヤー入りのラッピンググッズを使うと作業がしやすいです。
途中で井草が切れても、残り2本あれば大丈夫。
めげずにまきます。
がんばれ、がんばれ、
くるくる、ぎゅっぎゅっ。
14.次の画像は、私が良平堂さんから取り寄せた粽の持ち手を撮影した画像です。
良平堂さんのようにかっこよく・・・

15.都合で、しっかりまとめただけに・・・。
持って運ぶことはできました。

16.表から見るとこのような感じです

ちまきの作り方を写真付きレビュー!おすすめのレシピや口コミをご紹介
私は、今年は端午の節句のお祝いに、柏餅とちまきをの手作りに挑戦しました。
生地作りでは、柏餅の上用粉(上新粉)よりは、もち粉は扱いやすかったです。
笹や井草は、良平堂のちまきで使われている材料の方が立派だと思いました。
幅が大きく長さが短めの笹を使うと、良平堂のような格好の良いちまきが作れると思いました。
良平堂では、笹や井草のお取り扱いがないので、残念です。
翌日戴きましたが、笹の葉の香りとともにおいしいちまきを頂けてとても幸せを感じました。
ちまきの口コミでは、「食べる時にはがしにくい」という口コミがありました。
水気があればよいのかな、と、私はちまきに水をよくつけてから巻いたので、笹もきれいにはがしていただけました。
家族みんなでワイワイ言いながら作っていただく、
和菓子屋さんなどあまりなかった時代には、
このように家で手作りして端午の節句をお祝いしていたのだな、と感慨深い思いに浸りました。
ぶきっちょの私でもとてもおいしくできたので、あなたならもっと上手に作れますよ!(^^♪
ぜひトライしてみてくださいね!




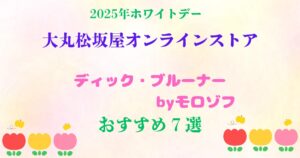



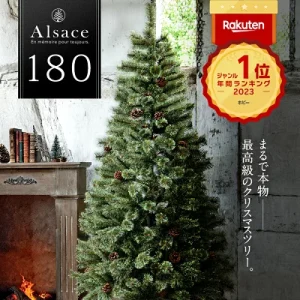



コメント